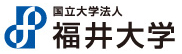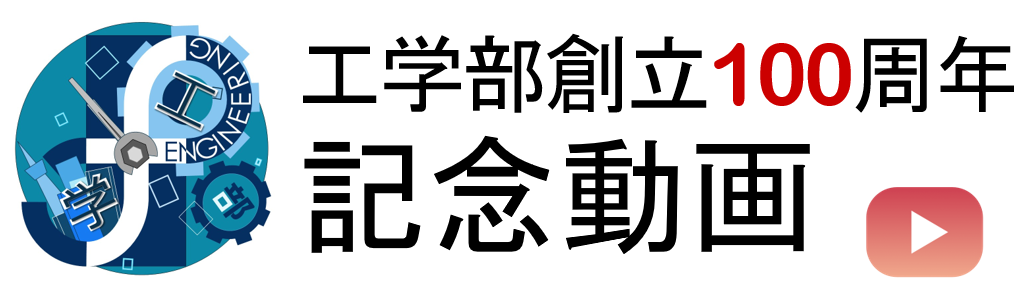工学部百年史概要
百年史編纂部会 部会長
2020年4月~2024年3月 橋本貴明
2024年4月以降 岡田将人
福井大学工学部は官立高等工業学校の1つとして1924(大正12)年に福井高等工業学校として創立され、1944(昭和19)年よりの福井工業専門学校を経て、1949(昭和24)年より福井大学の工学部として現在に到っています。詳細は百年史本編に譲りますが、多くの組織改革を行いながら100年の道のりを歩んできました。百年史では、この100年間で大学を超えて学部独自のアイデンティティを保ちながら発展してきた歴史を詳細に振り返ることができます。
福井大学工学部ではこれまで、創立50年を記念して「福井大学工学部五十年史」を発刊しています。歴史の大きな節目となる今回の百年史の内容をどのようにするかについて、2020年に発足した百年史編纂部会で検討を開始しました。その議論の結果、次のような基本方針のもとに編纂を進めることとなりました。
(目的)
福井大学工学部百年史を編纂することは、工学部自身の百年の来る所以を確かめ自己確認を行うことです。編纂されたものは、次世代へ向けての新しい工学部像を描く際の礎となり、また指針を与えるものとなります。
(具体的方針)
編集の基本方針は、この来る所以を確かめ自己確認を行うために、そもそもの由来、また100年間の中で何が引き継がれて来たか、時代に合わせて新たに何が加わってきたかを明らかにすることとしました。そのためには正確な史実の積み上げが重要となります。福井県や地域との係わり合いの中でも、同様に伝承、喪失、付加の事柄を明らかにしていくことです。
(百年史の意義)
福井大学工学部百年史は一般的な大学史から見れば本来一つの部局史ですが、これまでの100年の中で創立から4分の1に当たる25年間は、高等工業学校あるいは工業専門学校として一つの独立した教育・研究機関でした。戦後間も無く学制改革により新制大学の一部局である福井大学工学部となり、現在まで約75年間続いてきています。このような背景の中で高等工業学校時代の25年間と一部局として75年間を経た工学部の100年間を連続して振り返ることは、100年という節目としての意味のみならず、本学部を理解する上で重要な意義あることです。編集の具体的な取り組みは、以下の3項目としました。
1. 可能な限り史料の発掘・収集を進め、百年史記述のための資料とする。
2. 福井高等工業学校の創立から現在の福井大学工学部までの沿革を明らかにし、
これまでに起きた事柄を客観的に記述する。
3. 収集した史料そのものが重要な歴史的事実であるため、貴重な史料として保存に努める。
この百年史を編纂するにあたり、編纂部会では5年間を通して16回にわたる会議を開催し、執筆方針から構成、内容の確認を進めてきました。その過程で執筆に関わっていただいた方々は、実に140名以上に達します。その中には、既に退職された歴代の工学部長や関連組織である工学部技術部、産学官連携本部、遠赤外領域開発研究センター、附属国際原子力工学研究所、繊維・マテリアル研究センター、工業会の方々も含まれます。執筆以外にも記念大会で講演された本学卒業生の市川秀和先生(福井工業大学教授)から多くの本学に歴史に関わる史料の提供をいただきました。部会委員間の連絡調整等で担当事務部である工学系運営管理課、刷り上がり校正原稿や印刷等で創文堂印刷株式会社の方々にも多大なる御協力をいただきました。これら関係各位の労を惜しまない御協力により、百年史は500頁を超える充実した史料となり発刊を迎えることができました。
本史料が本学工学部100年の歴史を認識する機会として、手に取っていただくことができれば幸甚です。