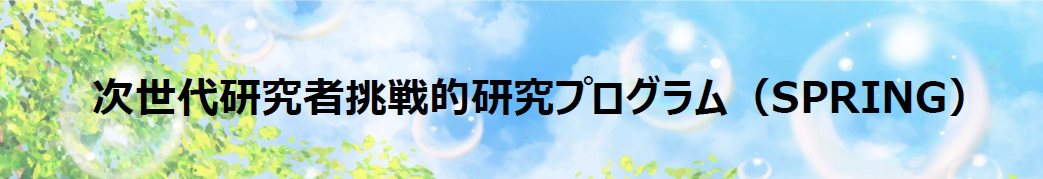教育理念
近年の急激な技術革新においては、個々の要素技術の開発においても、より学際的な基礎科学の助けが重要となっています。実際、最先端技術で思いがけない発明や発見を可能にするのは、各分野の専門知識ではなく、より広い分野にわたる基礎能力に基づいた総合的な発想力であると言われています。日々進歩する技術やその多様化に柔軟に対応していくためには、狭い専門分野に閉じこもることなく、幅広い分野の基礎的な能力が必要とされるのです。また、国境を意識せず幅広い世界で活躍できるグローバル人材の育成が社会から求められていますが、このような人材に必要とされるのは、語学力ばかりではなく、確固たる基礎学力を基に、自ら高度な知識や技術を獲得し、使いこなす能力です。
我が国の工業技術は、今後、豊かで安全・安心な社会の構築とその維持に貢献する必要があり、そのためには、ものごとを根本から論理的に考える能力・習慣を持ち、生涯にわたって自らの力で継続的に学び続ける力が重要です。
応用物理学科では、工学の幅広い分野に対応できる確固とした理工学の知識・思考方法・応用能力を修得するとともに、総合的な実践力や産業関連知識を自ら学び、課題解決につなげる力、グローバルな行動力、倫理観を身につけた人材を養成します。物理学を中心とした基礎科学と工学との接点に立って総合的な発想力と応用力を養うことにより、新しい技術の創出に挑戦するとともに、来るべき未知の技術革新にも対応し、安全で安心な社会を真に支える先端技術者の育成を目指します。
ディプロマ・ポリシー(DP:学位授与の方針)
工学部 学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
工学部では,大学の目的等を踏まえ,安全で安心な社会の創造に寄与することを目的に,その創造のための基礎的な知識・教養,幅広い専門知識に裏打ちされた高度な専門能力,さらに歴史や文化,習慣の違いを超えて世界の人々と協働し,倫理観を持ち主体的に行動できる総合的な能力を備えた高度専門技術者を養成します。
この人材養成目的を踏まえ,工学部では,以下の知識・能力等を修得するとともにそれらを課題の解決において活用・実践できる者に学位を授与します。
(a) 安全・安心社会を創造するための基礎としての数学や自然科学に関する知識・能力
(b) 各分野の専門技術者として国際社会の中で責任を果たすための専門知識・能力
(c) 産業実践力も含め,多様な学問分野にかかわる幅広い知識・能力
(d) 夢を形にする高度専門技術者に求められる創造力,自己学修力,問題解決能力,協調性,およびコミュニケーション能力を併せた総合力
(e) 技術者として守るべき倫理や負うべき社会的責任に関する理解
学士力との対応関係
| 1. 知識・理解 | 2. 汎用的技能 | 3. 態度・志向性 | 4. 総合的な学習経験と創造的思考力 | |
| (a)数学・自然科学 | 〇 | 〇 | ||
| (b)専門 | 〇 | 〇 | ||
| (c) 広い知識・能力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| (d)総合力 | 〇 | 〇 | ||
| (e)倫理・社会的責任 | 〇 | 〇 |
学士力
1. 知識・理解(文化,社会,自然 等)
2. 汎用的技能(コミュニケーションスキル,数量的スキル,問題解決能力等)
3. 態度・志向性(自己管理力,チームワーク,倫理観,社会的責任等)
4. 総合的な学習経験と創造的思考力
応用物理学科における学位授与の方針は,工学部の方針のもと,卒業後の進路先等社会のニーズを踏まえ,以下の通りとなります。
<応用物理学科>
以下の知識・能力等を修得するとともにそれらを課題の解決において活用・実践できる者に学位を授与します。
(APa) 物理学を中心とした理工学の確固たる基礎知識と,それらを応用する能力
(APb) 基礎知識に基づいてものごとの本質を捉えた上でその知見から総合的に発想し,未知の技術革新に対応できる能力
(APc) 新しい知識・技術を自ら学び,計画的に課題の解決に取り組む能力
(APd) 他者とコミュニケーションをとることや、協力してプロジェクトを進めることができる能力
(APe) 工学部の(e)と同じ
カリキュラム・ポリシー(CP:カリキュラム編成の方針)
学生が学習していく中で学位授与の要件を満たす人材となるよう、工学の基礎となる物理学を中心にカリキュラムを編成しています。具体的には、工学部共通の項目と、応用物理学科の専門の項目を習得・達成できるようカリキュラムを構成しています。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)に沿って受け入れた学生に対し、学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げた人材を養成するため、本学の教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)および以下に述べる工学部の方針に従って、教育課程を編成するとともに、教育を実施し、学修成果を厳格に評価します。
(1) 教育課程の編成方針
① 教養教育を担う「共通教育科目」と専門教育を担う「専門教育科目」を開設します。教育課程全体を通してディプロマ・ポリシーに掲げた能力等の達成が担保されるよう、各科目の目的や到達目標を設定します。科目の配置(共通教育及び専門教育の配分、必修科目・選択科目の配当等)は、「共通教育の教育課程編成の方針」および以下の方針のもと、順次的・体系的に行います。
② 「産業実践力」と「国際教養力」に関する科目群を、共通教育科目と専門教育科目を横断して配置します。
③ 専門教育科目は「専門基礎科目」と「専門科目」により編成し、低学年時に専門にかかわる幅広い基礎知識を身に付け、学年が進むにつれてより専門性の高い知識を身に付けられるよう配置します。
④ 専門基礎科目は、工学全般の基礎として必須である数学や物理等の科目、産業実践力に関する科目、国際教養力に関する科目等で構成します。
⑤ 専門科目は「学科専門科目」、「コース専門科目」、「卒業研究」により構成します。学科専門科目は、各学科の基礎(すなわち、工学のオーソドックスな一つの分野の基礎)の学修を通して確かな専門基盤知識・技能を修得させることを主な目的とします。コース専門科目は、複数のコースをもつ学科に配置され、コースで必要な専門知識・技術および各分野の技術の展開力の基本を修得させることを目的とします。
⑥ 4年次に卒業研究を通年の必修科目として配置します。
⑦ 初年次教育を充実させるための必修科目を、共通教育及び専門科目に配置し、大学での主体的な学びに必要となる基礎的な素養等を修得させるとともに、将来のキャリアについて考える手がかりを与え、学びの動機づけを強化します。
⑧ 産業実践力の中でも特に技術経営等についてより深く体系的に学びたい学生のために、副専攻を設けます。
⑨ 原子力、放射線、環境、エネルギー、技術者倫理を体系的に学ぶことができる副専攻を設けます。
⑩ 知識・技能を総合して問題を解決する実践的能力を育成するため、創成教育の科目を設けます。
⑪ 教育課程の水準は、高等学校等までの学修内容、学術の発展動向、学生や社会の意見・ニーズなどを踏まえて設定します。
(2) 教育課程における教育・学修方法に関する方針
① 教育効果を高めるため、授業は、その内容や目的に応じ、講義、演習、実験・実習あるいはこれらの併用により行います。
② 実験・実習、演習等では少人数教育を行います。
③ 主体的に学ぶ力を高めるため、実験・実習、演習ではアクティブ・ラーニングを前提とした授業を実施するとともに、講義にも積極的にアクティブ・ラーニングを取り入れます。また、PBL 型の授業、学科横断型の授業、学修支援システムを活用した授業、インターンシップ、海外への短期留学など、多様な形態の授業を実施し、講義だけでは涵養することが難しい能力・技能等の育成を図ります。
④ 卒業研究では、専門知識を活用して課題を解決することを通し、総合的な実践力を育成します。卒業研究の指導と評価にあたり、主指導教員を定めるとともに必要に応じ副指導教員を定めます。
⑤ 学修時間が確保されるよう、準備学修等の指示、組織的な履修指導、履修登録できる上限単位数の設定、オフィス・アワーの設定、自習室の設置などを行います。
⑥ 全ての授業において、授業の目標、授業内容、授業方法、到達目標、評価の方法、教科書・参考書、準備学修等の具体的な指示等が記載されたシラバスを作成し、学生に周知するとともに、シラバスに従って授業を実施します。
⑦ 組織的なFD 活動により、教育方法の継続的な改善に取り組みます。
(3)学修成果の評価の方針
① 授業科目(卒業研究を含む)の成績評価は「福井大学における多面的かつ厳格な成績評価のガイドライン」に沿って行います。科目ごとの詳細はシラバスに記載します。
② 卒業研究については、ディプロマ・ポリシー等の観点から、複数の教員により評価を行います。
③ ディプロマ・ポリシーに掲げた能力等の評価は、授業科目(卒業研究を含む)の成績評価を総合化して行います。
教育課程のうち主に専門にかかわる部分について、応用物理学科の方針は以下の通りです。
(1) 教育課程の編成方針
① 1年次には、カリキュラムを概観する科目、その学修に必要な数学、物理の基礎的科目を中心に配置します。
② 2年次には、物理学におけるやや専門的な科目として、物理・数学・計算機科学の科目を中心に配置します。
③ 3年次には、理工学の確固たる基礎知識とそれらを応用する能力を身に付けるため、応用物理学分野を含む、専門的な物理系科目を中心に配置します。
④ 2~3年次には、物理学を中心とした理工学の理解を深めるため、物理・化学系科目を配置します。
⑤ 1~3年次には、実験に必要な技術や、レポート作成に必要な、文章、図表、数式、プログラム等で表現する能力の修得、課題を計画的に進め、期限内にまとめる能力を育成することを目的とする実験科目を配置します。
⑥ 技術者がグローバルに活躍する上で必要な技術英語に係る科目を配置します。
(2) 教育課程における教育・学修方法に関する方針
① 数学系・物理系・計算機科学系の基礎的科目には、演習科目を設け、さらに講義と演習を発展的に組み合わせた講究授業を行うなどの工夫により、定着を図ります。
② 実験科目では、自然科学の基礎的実験から、先端工学まで、学修内容を踏まえたテーマ設定により、理工学に係る実験技術等を段階的に修得させます。また、一定の期間をかけて少人数チームでテーマに取組ませることにより、計画性、協調性、コミュニケーション能力などの涵養も図ります。
③ コンピュータサイエンスと、数学・物理学・化学との融合を目指し、計算機科学系科目では、講義科目と実験科目の連携を行います。
④ 実験科目と卒業研究では、自主的・継続的に学修し、文献等を調べながら、自ら知識を獲得できる能力を育成します。
応用物理学科では、ディプロマ・ポリシーに掲げる目標を着実に達成するためのカリキュラムを作成し、継続的に改善しています。実際のカリキュラムは、こちらをご覧下さい。
JABEEについて
応用物理学科では、JABEEの認定・審査申請を予定しており、JABEEの認定基準に準拠した教育プログラム(応用物理学プログラム)に基づいて教育を行っています。JABEEの詳細については、認定機構のホームページを参照してください。